
冬至にはかぼちゃを食べるもの。
だけど、なぜ冬至にかぼちゃを食べるのでしょう。
日本の行事、冬至の行事食としてのかぼちゃについて確認しておきましょう。
冬至にかぼちゃは食べるもの
冬至に食べる食べものといえばかぼちゃですよね。
今年はいつ食べればいいのかといいますと、2015年(平成27年)の冬至は、12月22日です。
冬至とは、二十四節気のひとつで、一年中で日照時間が一番短い日のことです。
ということは、冬至の翌日からは日照時間が伸びていくということ。
「一陽来復」といって、悪いことが続いてもこの日を境に運が好転してくれます。
冬至にかぼちゃを食べる理由
日本では、季節に応じて自然のチカラを上手に生活に取り入れていました。
冬至の行事食として、食事にかぼちゃを食べるようになりました。
たくさん種類のある野菜の中から選ばれたかぼちゃ。
なぜ、かぼちゃを食べるのでしょう。
かぼちゃの収穫時期は夏なので、冬とは関係なさそうですが、かぼちゃは保存がききますよね。
昔は、冬の食べ物が少なかったので、栄養を摂るためにかぼちゃを食べていたのでしょう。
かぼちゃには、カロテンやビタミンAが豊富なので、
冬至に食べると風邪の予防や動脈硬化の予防になるといわれています。
冬至にかぼちゃで運が付く由来
冬至にかぼちゃを食べると「運」が付くって言われています。「ん」は「運」
が呼び込むと考えられていて、にんじん、れんこん、うどん、ぎんなん、
きんかん、かんてんなどを食べると縁起がいいんですね。
もちろん、かぼちゃもなんですけど、
かぼちゃには「ん」が付かないじゃないか!って思うかもしれませんね。
かぼちゃの別名は「南京(なんきん)」
だから、かぼちゃが「ん」のつく食べ物。
それも「ん」が2つもつく、縁起がいい食べものなんですね。
まとめ
昔から続く「冬至を祝う」という日本の行事。
寒い冬に対処する昔の人の知恵が込められているのでしょう。
冬至にかぼちゃを食べて、冬を乗り切っていきたいですね。
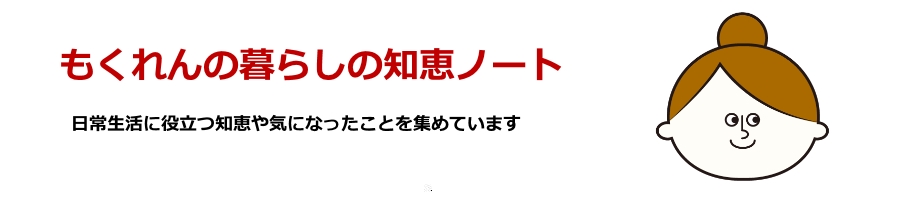



コメント